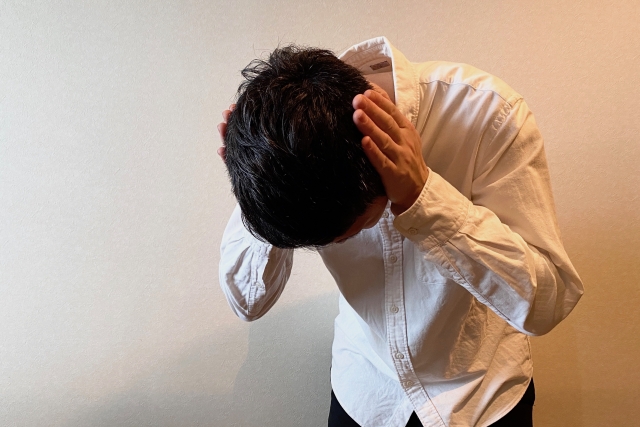動物は歯を磨かないのに、なんで人間は?──歯磨きのはじまりと、人間らしさのゆくえ

こんにちは。Sol@です。
毎日の歯磨き。
朝起きて、夜寝る前に、シャカシャカと。
でもふと思ったんです。
「動物って歯磨きしないよね……?」
「なのに、なんで人間は磨かないと不快になるんだろう?」
「そもそも、いつから磨くようになったの?」
今回はそんな“当たり前すぎて見えなかった問い”を、
ゆっくりコトトコしてみたいと思います🪥
1. 動物はなぜ歯を磨かなくても平気なの?
猫も犬もサルも、歯ブラシなんて持ってません。
野生動物が「歯のケア」をしている様子も、ほとんど見かけませんよね。
でも実は、虫歯や歯周病になる動物もちゃんといるんです。
✅ 動物の歯が健康を保ちやすい理由:
- 食生活が違う:肉や草など、加工されていない食べ物
- 噛む回数が少ない:すばやく飲み込むように食べる
- 唾液の性質:殺菌作用が強く、虫歯菌が繁殖しにくい
- 歯の寿命=命の寿命:多くの動物は歯が悪くなる前に寿命がくる
🐾 とはいえ……
- ペット化された犬や猫は虫歯にも歯周病にもなる
- 「犬の歯磨き」も今では当たり前に推奨されている
→ 人間と同じような食事をすると“人間の病気”になるってことなんです。
2. じゃあ人間は、なぜ不快に感じるの?
歯を磨かないと、口の中がネバつく・臭う・気持ち悪い……
これって動物にはなさそうな感覚です。
✅ 人間の生活環境が違いすぎる!
- 食べ物に砂糖が多い(虫歯菌の大好物)
- 1日3食+おやつで口の中がずっと活動中
- やわらかいものをよく噛まずに食べる
→ 食べかすや歯垢が溜まりやすく、細菌が繁殖しやすい口内環境になるんです。
さらに、
✅ 「ニオイ」や「不快感」を気にする感覚は、社会性と清潔観念の産物
- 他人と接する時の印象=「口臭はNG」という文化
- 「すっきりする=気持ちいい」という経験の積み重ね
→ つまり、「不快に感じるようになった」のは、文化と習慣による学習なんです。
結局一日三食って多いの?ちょうどいいの??
3. 歯磨きって、いつからあったの?
実は歯磨きの歴史はとても古いんです!
🏺 古代の歯磨き事情
- 古代エジプト(紀元前5千年頃)
→ 小枝の先をほぐして歯をこすった「歯木」が登場 - インド・中国でも類似の習慣が
→ 漢方や塩、香料などで口をすすぐ習慣あり - 日本では平安時代から「塩で歯を磨く」文化
→ 江戸時代には「房楊枝(ふさようじ)」という歯ブラシに近い道具も
そして19世紀、近代的な歯ブラシと歯磨き粉が登場して、
20世紀に「口腔ケア=健康」のイメージが強まり、今に至るのです。
4. 歯磨きの「気持ちよさ」はいつ生まれた?
最初は「口臭を抑える」「虫歯を防ぐ」ためだった歯磨き。
でも現代では、「磨かないと気持ち悪い」「シャカシャカしないと落ち着かない」という感覚すら生まれています。
これはつまり、
✅ 歯磨きの“清潔感”や“すっきり感”が、文化として体に染み込んだ証拠
ある意味では、
歯磨きの「快感」すらも“発明された価値観”とも言えるのかもしれません。
5. まとめ:歯磨きは、「文化を受け入れた証」なのかもしれない
- 動物は磨かなくてもそこまで困らない(でもペットは別)
- 人間は生活環境・食べ物・社会性の中で「磨く必要」が生まれた
- 歯磨きは古代から存在し、時代と共に“快適さ”として進化してきた
- 現代人の「磨かないと不快」は、文化と習慣が作った“新しい感覚”
毎日何気なくしているシャカシャカ。
でもそれは、自然から離れた人間の“新しい本能”かもしれません。
「不快だから磨く」のではなく、
「磨くのが普通だから、不快になる」。
そんな風に、私たちの身体の感覚って、社会と共に進化してきたのかもしれませんね。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました!
それではまた、次のコトトコでお会いしましょう🪥✨