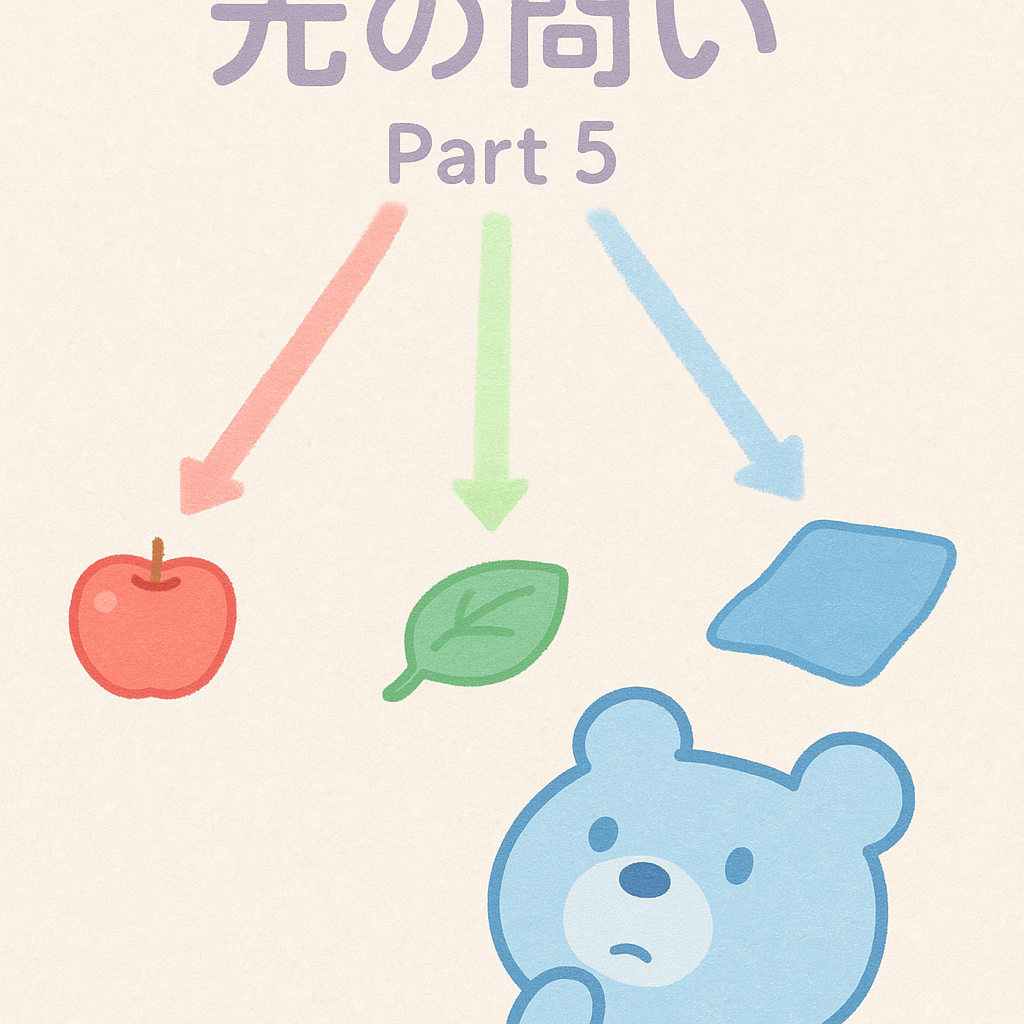なぜ人は、痛みを測ろうとしたのか?──痛みをめぐる歴史
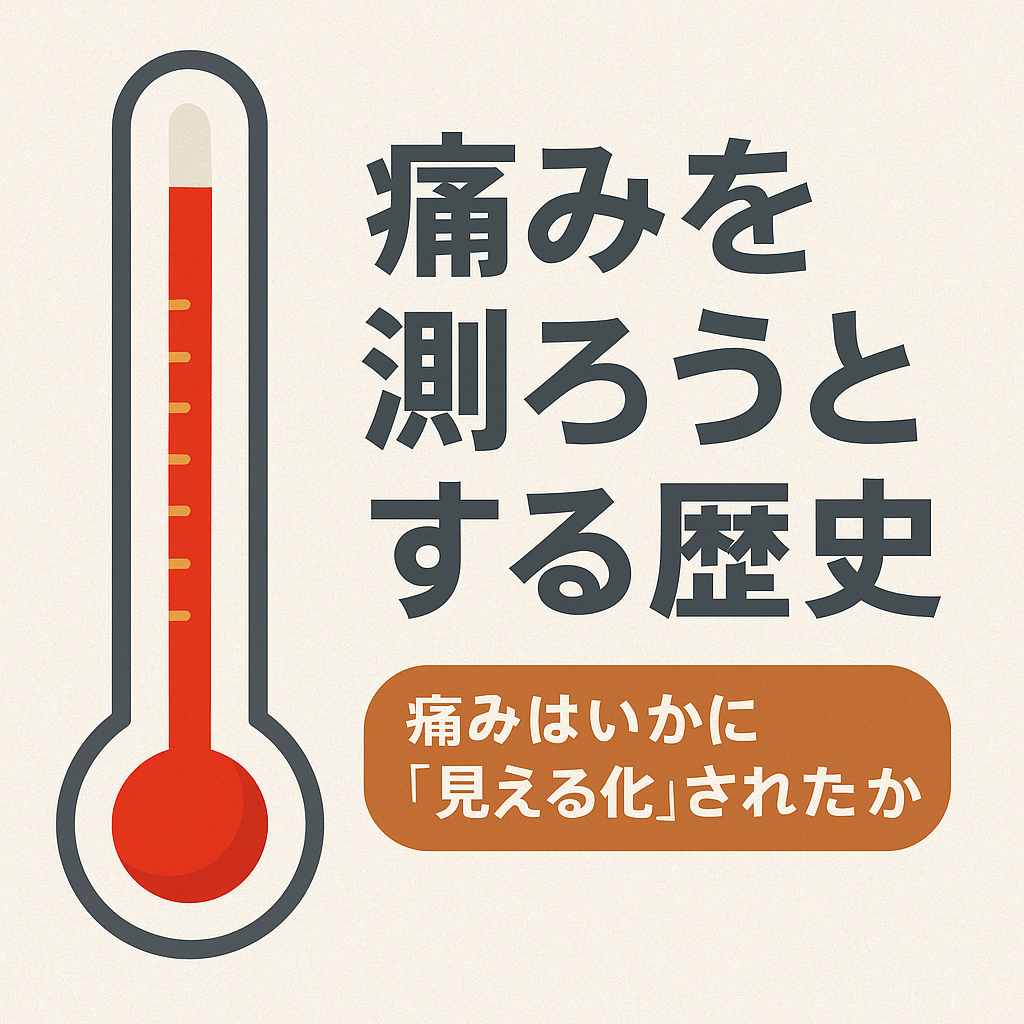
こんにちは。Sol@です。
前回、「痛みには単位がない」という話をしました。
前回リンク:痛みは数えられるのか?──痛みの単位を探して
測れないのに確かに存在するもの──それが痛み。
でも、だからこそ人間は、
この見えない感覚を、どうにかして「測ろう」と挑み続けてきたんです。
今回は、そんな痛みを測ろうとした歴史の物語をコトトコしてみたいと思います!
1. 痛みは「祟り」だった時代
古代の世界では、痛みは科学ではなく、
「呪い」や「罰」として理解されていました。
- 痛み=悪霊の仕業
- 痛み=神様の怒り
そんなふうに捉えられていた時代には、
当然ながら、痛みを「数える」発想は生まれません。
痛みは、
耐えるもの、祈るもの、祓うもの。
つまり、
数える対象ですらなかったんです。
「数える」って、実はすごく人間らしい進化だったのかも。
2. 医学の登場──痛みは「症状」として扱われる
やがて、医学が発展してくると、
痛みは「病気のサイン」として捉えられるようになります。
たとえば──
- 古代ギリシャのヒポクラテスは、痛みを「身体の異常」の結果と考えた。
- 中世ヨーロッパでは、痛みの場所や質を記録する習慣が生まれた。
でも、まだ「どれくらい痛いか」を数値で表す方法は存在しません。
このころの痛みは、
▶️ どこが痛いか
▶️ どんなふうに痛いか
を言葉で伝えるものでした。
「どんな風に痛いか」って難しいよね?
3. 数値化の始まり──近代の医療へ
近代になると、科学と技術の進歩とともに、
「痛みも数値で扱えないか?」という発想が本格的に出てきます。
たとえば──
- 19世紀:手術や麻酔の発展で、「痛みを抑える技術」が重要視される
- 20世紀:ペインスケール(痛み評価尺度)が開発される
▶️ 「0〜10で痛みを表す」みたいなアイデアが出てきたのは、ここから!
最初はシンプルな数直線だったけれど、
やがて、
- 顔の表情(フェイススケール)
- 質的評価(ズキズキ、チクチクなど)
も組み合わされるようになりました。
▶️ つまり、痛みは単なる「量」ではなく、
▶️ 「質」や「感情」も大切な要素だとわかってきたんです。
4. まとめ:「痛みを数えたい」という願い
今日のコトトコをまとめると──
- 古代では、痛みは「神や悪霊のしわざ」だった
- 医学の発展とともに、痛みは「症状」として扱われるようになった
- 近代になって、痛みを「数値化」しようとする試みが始まった
- 痛みは量だけでなく、「質」や「感情」も含んでいる
人は、目に見えない痛みを、
どうにかして言葉に、数に、形にしようとしてきた。
それはきっと──
誰かの痛みを、少しでも理解しようとする、静かな優しさだったのかもしれません。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました!
それではまた、次のコトトコでお会いしましょう🌱✨