なぜ音階は「ドレミファソラシド」なの?──言葉と音がつながった、祈りのはじまり
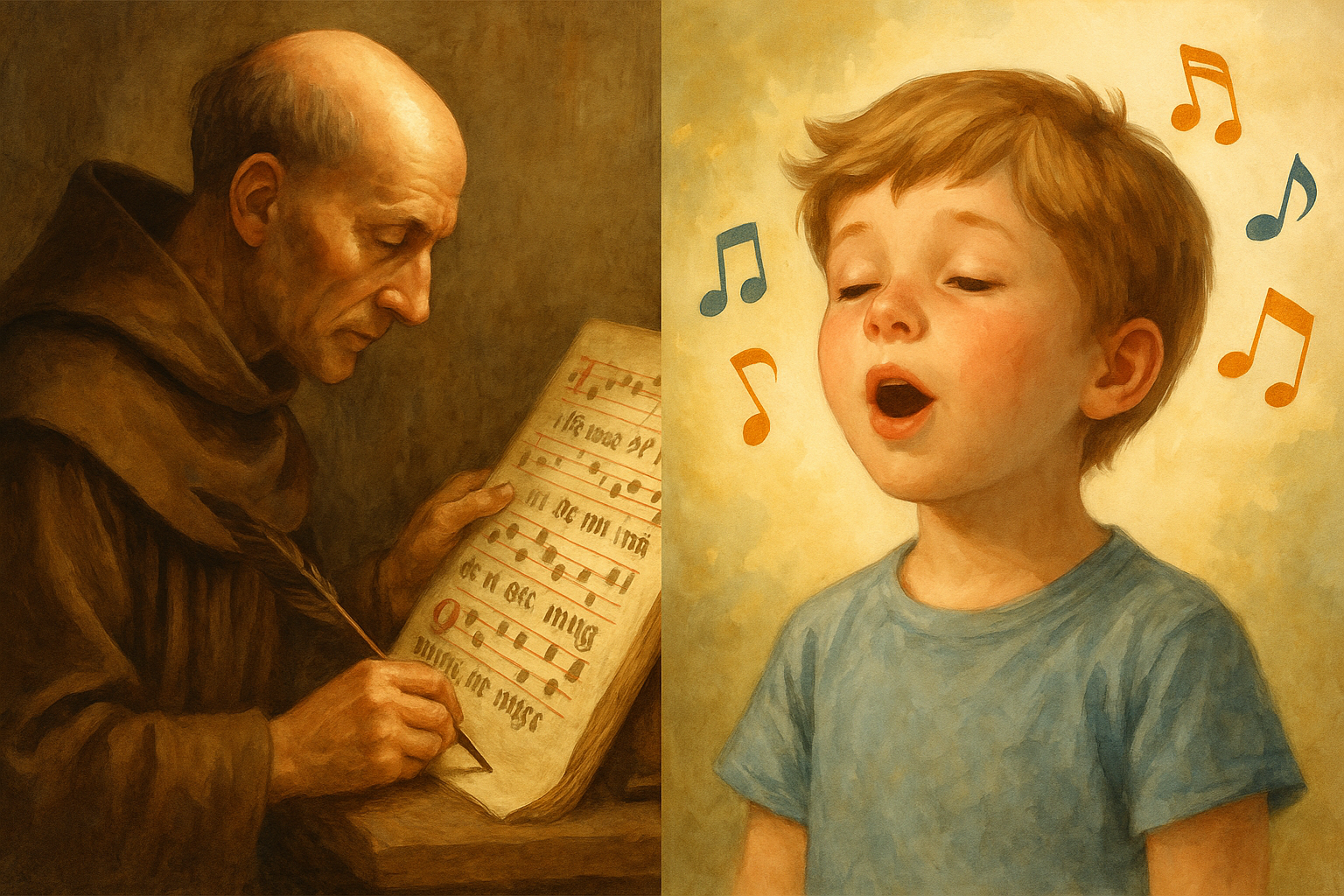
こんにちは。Sol@です。
私たちがあたりまえのように使っている音の名前、
「ドレミファソラシド」。
音楽の授業で自然に覚えて、
階段みたいに上がって、また戻ってくるあの音階──
でも、ふと気になったんです。
「なんで、ドレミファソラシド」なの?
誰が決めたの?どうして“カキクケコ”じゃないの?
今回はそんな素朴な疑問を出発点に、
“音の名前”のはじまりを、歴史とともにコトトコしてみたいと思います🎶
1. ドレミファソラシドって、なんでそう呼ぶの?
まず結論から言うと──
この「ドレミファソラシド」は、11世紀ごろの中世ヨーロッパの修道士たちによって生まれたもの。
そしてその原型は、なんと──
ラテン語の賛美歌の歌詞なんです。
2. はじまりは中世の修道院から
音階の語源となったのは、イタリアの修道士
グイード・ダレッツォ(Guido d’Arezzo)。
彼は音楽教師として、当時の修道士たちに賛美歌を教えていました。
しかし当時は楽譜の概念も曖昧で、曲を教えるのがとても大変だったのです。
そこで彼は考えました。
「もっと効率的に“音の高さ”を教える方法はないか?」
そして彼が発明したのが──
「音の高さごとに名前をつけて覚える」という画期的な方法。
これが、現代に続く「音階教育」のはじまりでした。
そういえば楽譜っていつできたんだろうね?
3. 賛美歌の歌詞が音階になった?
グイードが注目したのは、ある有名なラテン語の賛美歌。
その名も──
Ut queant laxis(ウト・クエアント・ラクシス)
この賛美歌の歌詞は、実は最初の6つのフレーズが順番に1音ずつ高くなっている構造だったのです。
その冒頭部分がこちら👇
Ut queant laxis(ウト)
Re sonare fibris(レ)
Mi ra gestorum(ミ)
Fa muli tuorum(ファ)
Sol ve polluti(ソ)
La bii reatum(ラ)
→ それぞれのフレーズの最初の音節が、音階の語源になったんですね!
「1音」ってどうやって定義するんだろう??
4. “ド”や“シ”はあとから変わったの?
さて、ここで気づいた方もいるかもしれません。
元の音階は──
Ut・Re・Mi・Fa・Sol・La
あれ、「ド」と「シ」がない……?🤔
✅ 「Ut」は「Do」へと変化
「Ut(ウト)」は発音しづらかったため、
後の時代により歌いやすい「Do(ド)」へと置き換えられました。
この「Do」は、
- ラテン語で「主」を意味する Dominus に由来する説
- または単に発音のしやすさ重視で選ばれたという説
があると言われています。
✅ 「Si」は“聖ヨハネ”から生まれた?
「Si(シ)」は、グイードの時代にはまだ存在していませんでした。
でも7つ目の音を表す必要が出てきたとき、
人々はこの賛美歌の続きの言葉から──
Sancte Ioannes(聖ヨハネ)
の頭文字「S」と「I」を取って「Si」を作り出しました!
(ちなみに英語圏では、混同を避けるため「Si」ではなく「Ti」と表記することもあります)
5. 音階と記憶、ことばと音の不思議な関係
こうして生まれた「ドレミファソラシド」。
もともとは“歌の練習用の記号”だったはずの音階が、
やがて「音の名前」として世界中に広まり、
今では音楽の土台として当たり前のように使われています。
不思議ですよね。
言葉が音を整理し、音が言葉のようになっていった。
- 覚えやすい音節を選ぶ
- 歌詞のメロディに乗せる
- ラテン語の美しさを活かす
それはまるで、記憶と祈りのあいだに音楽が生まれたような物語です。
戦時中に英語が使えないときも「ドレミ……」だったのかな?
6. まとめ:音階は、祈りの中から生まれた
- 「ドレミファソラシド」の起源は、中世のラテン語の賛美歌
- イタリアの修道士グイード・ダレッツォが教育のために作った記法がはじまり
- “Ut”は後に“Do”へ、7番目の“Si”は「聖ヨハネ」から
- 覚えやすい音節を使ったことで、音が「ことば」になった
- 音階は、音楽を“記憶できるもの”へと変える手がかりだった
いつも何気なく口ずさんでいた「ドレミファソラシド」。
その背後には、祈りと教育、そして言葉と音の深いつながりがありました。
次に「ドレミ……」とつぶやくとき、
その音がたどってきた千年の旅路を、ほんの少しだけ思い出してもらえたら嬉しいです。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました🎵
それではまた、次のコトトコでお会いしましょう!







