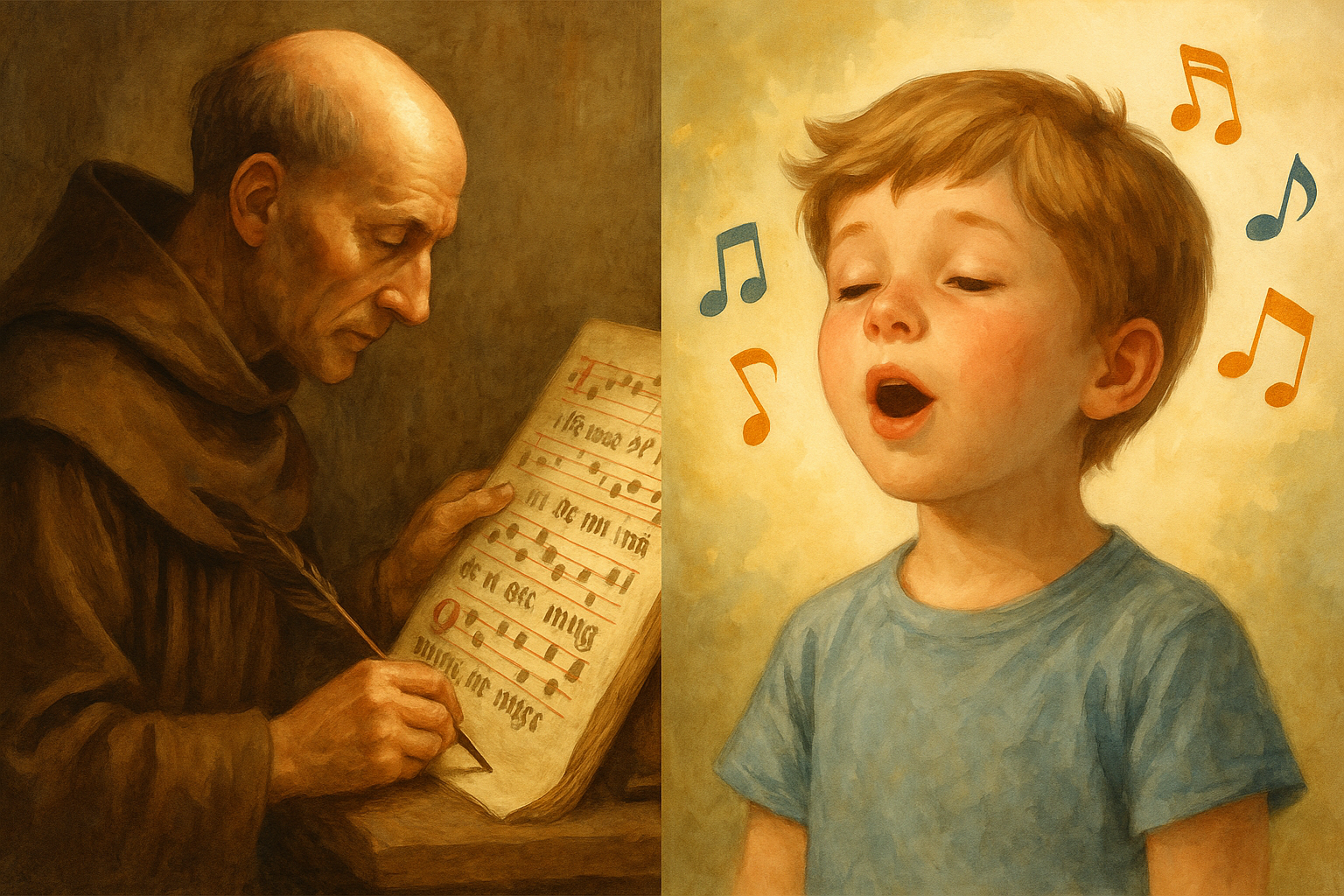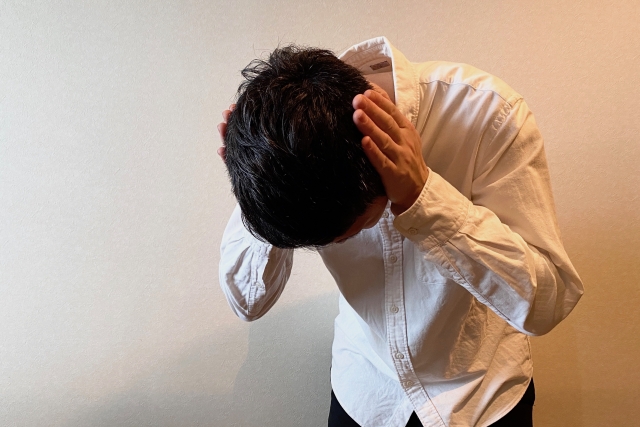「味覚がマヒした」ってほんと?──わさびとコーヒーの“好き”のしくみ

こんにちは。Sol@です。
昔は「絶対ムリ!」だったのに、
大人になってみたら「案外イケるかも……?」って思う食べ物、ありませんか?
わさび、コーヒー、ビール、ピーマン、ゴーヤ……
なんだか共通して「苦い」「辛い」「渋い」ものが多いような?
そしてそんなとき、よく言われるのがこのセリフ。
「味覚がマヒしてきたんだよ」
……でも本当に、舌が“マヒ”してるだけなんでしょうか?
今回はそんな問いをもとに、「味の好みが変わる」ことの正体をコトトコしてみました。
1. 苦手だった味が平気になる現象
まず、事実として「味覚が変わる」ことはよくあること。
- 子どもの頃はわさびや辛子が苦手だったのに、大人になったら大好きに
- ブラックコーヒーが“おとなの味”に感じられるようになる
- 苦味や酸味、渋みに“奥行き”を感じるようになる
これは一体、何が変わったからなのでしょうか?
2. 舌がマヒしてきているってどういうこと?
よく言われる「味覚のマヒ」は、実は少しだけ事実です。
✅ 舌の“味蕾(みらい)”は年齢とともに減っていく
味を感じる細胞「味蕾」は加齢により少しずつ減少します。
その結果、味の刺激に対する感度がやや鈍くなる傾向はあります。
とくに苦味や渋みといった“拒絶系”の味に対して、
子ども時代のような強い反応が出にくくなるんです。
→ だから「苦いものが大丈夫になった」は、
ある意味で“マヒ”も一理ありなんですね。
味蕾っていくつくらいあるんだろう??
「子供が親より味に敏感」って生存に有利??
3. でも、実は“脳”で味わってる?
でもここでひとつ、見逃せない事実があります。
味覚は「舌」だけじゃなく「脳」が感じている。
たとえば──
- わさびのツーンとした刺激は「味」じゃなく「痛み」
- コーヒーの苦味だけでなく「香り」や「酸味」「喉ごし」も評価の一部
- 味とセットになっている「経験」や「イメージ」が“おいしさ”に影響する
つまり、私たちの味の好みは
感覚の変化と同時に、認知の変化でもあるということ。
あなたの一番おいしい「シチュエーション」は何??
4. わさびとコーヒーのケーススタディ
🟢 わさびの場合:
- 「刺激物」=アリルイソチオシアネート(辛味成分)
- 刺激に“慣れる”ことで、耐性ができる
- 刺激の奥にある「風味」や「余韻」に気づけるようになる
→ 初めは「辛っ!!」だけだったのが、
「寿司やそばとの相性」という文脈ごとの味わいに変わっていく。
☕ コーヒーの場合:
- 苦味=カフェインやクロロゲン酸など
- 初めて飲むと「にがっ!」→ 何度か飲むと「香ばしい」「香りが良い」
- 大人の世界の象徴的なイメージも、味覚に影響
→ 経験や社会的な認知が、味の感じ方そのものを変えていく。
5. マヒ?成長?問いの味わいかた
結局のところ、「苦手な味が好きになる」のは──
- 少しだけ“マヒ”した舌の変化
- でも、より大きな要因は“脳と経験”のアップデート
「苦味=毒」と判断していた子ども時代の脳が、
「苦味=深い味わい」や「大人の美味しさ」と捉えるように変わる。
それは、「味覚が劣化した」というよりも、
“味を構造的に楽しめるようになった”とも言えるかもしれません。
6. まとめ
- 味蕾の数は年齢とともに減る=感度の低下(軽いマヒ)は起きる
- でも、味の好みの変化の大部分は「脳と経験」によるもの
- わさびやコーヒーは、刺激の奥に“味の意味”を見出せるようになって好きになる
- 「まずい→おいしい」への変化は、舌の変化だけじゃない
- 味覚の変化は、「成長」でもあり、「世界の広がり」でもある
子どものころは「なんでこんなもん食べるの?」って思っていたものが、
いつのまにか「これ、意外とイケるじゃん」になっていた。
それって、舌が鈍くなったんじゃなくて、
世界にもうひとつ“おいしい”を見つけられるようになったってことなのかもしれません。
次にコーヒーを飲むとき、
その苦さの奥にある「変化の物語」を味わってみてください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました☕🌿