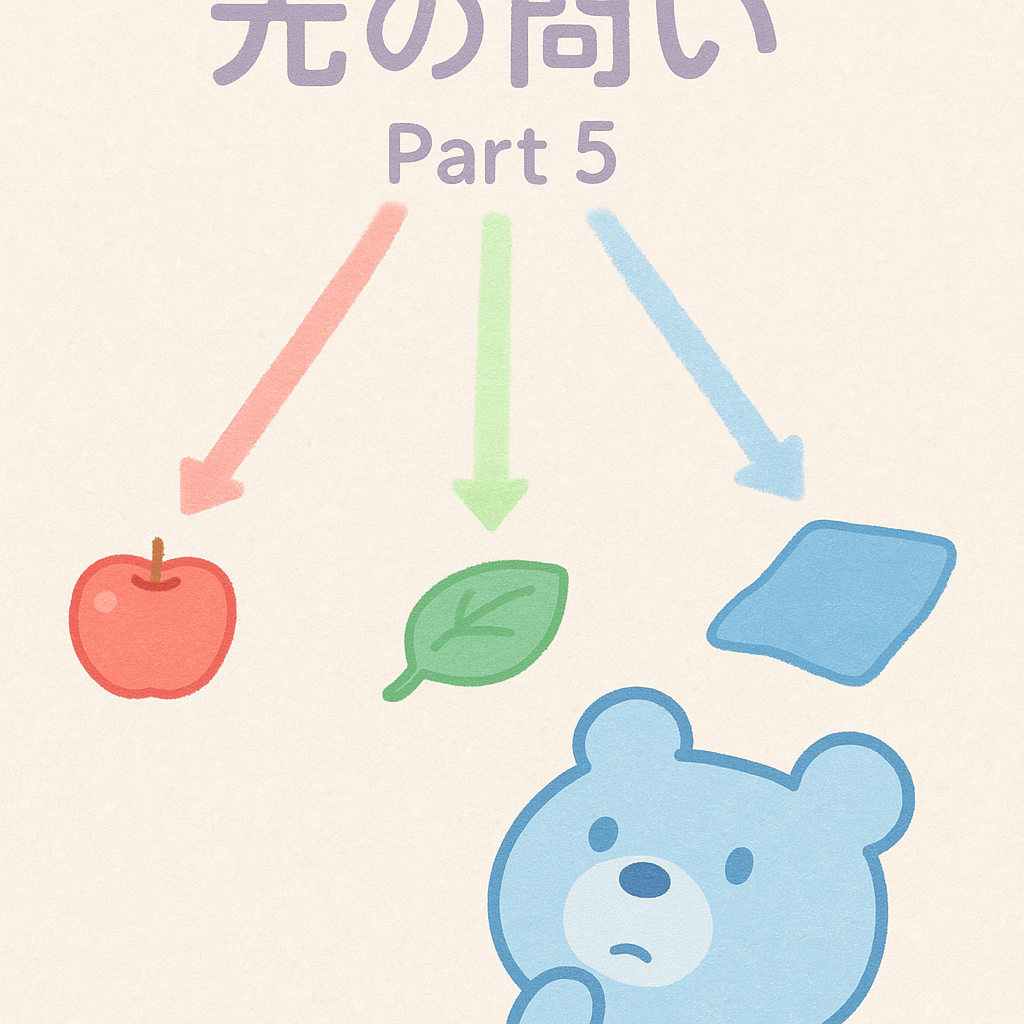光って、粒なの?波なの?……なんなの!?
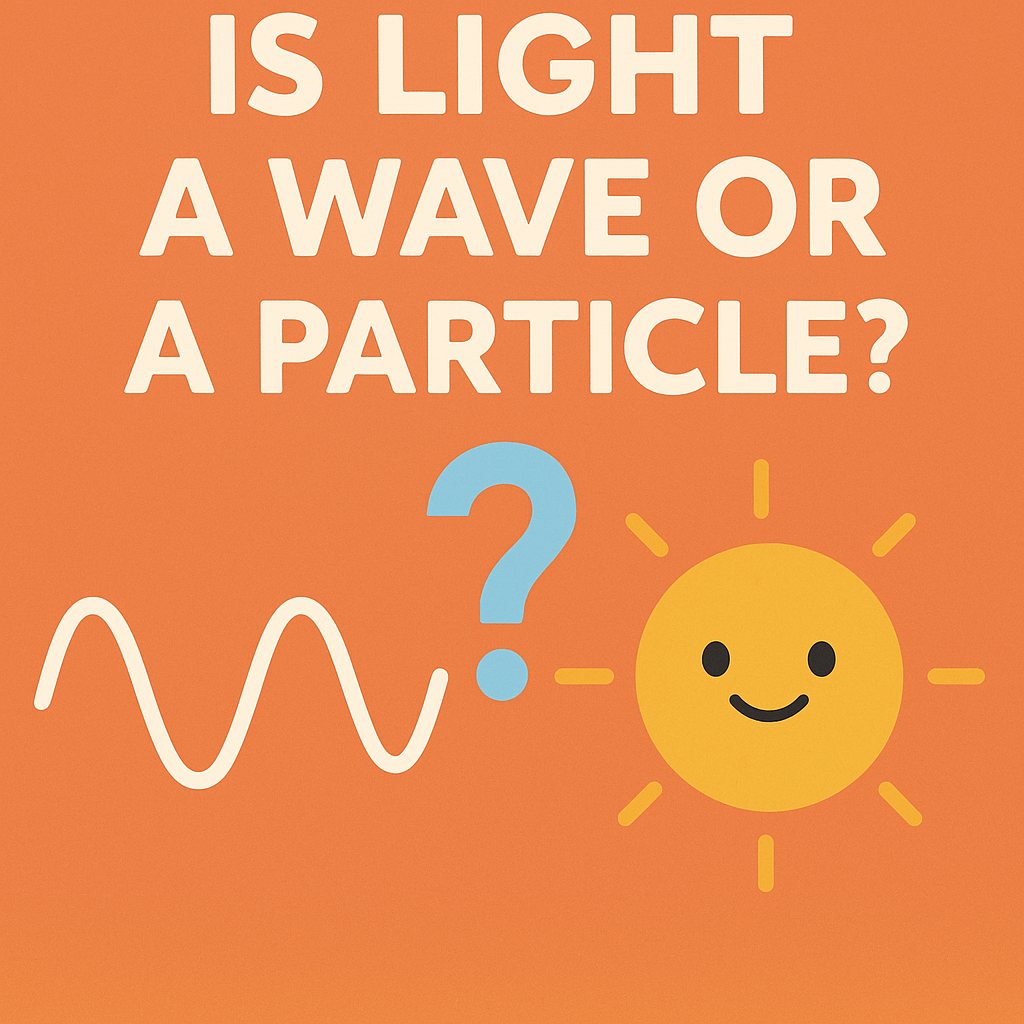
こんにちは。Sol@です。
お風呂でお湯を見つめていたときのことです。 ぼんやりと水面に反射する光を眺めていたら、ふと、疑問が浮かびました。
「光って……なに?」
明るいもの? 速いもの? あたたかいもの? どれも正しいようで、どれも本質に届かない気がします。
今回のコトトコでは、そんな「光って何?」という素朴な疑問を出発点に、 とても不思議で、ちょっと混乱してしまう問いに挑みます。
「光って、粒なの?波なの?」
いざ、出発です。長い旅路になります。準備をしっかりお願いしますね!
1. 光は波だと思われていた
かつて、光は波だと考えられていました。 水面の波や音のように、何かを伝える「波動」であると。
「波だからこそ、曲がったり、重なったり、広がったりするんだ!」 というわけですね。
たしかに、光はレンズで曲がるし、CDの表面に虹が出るし、 シャボン玉の膜も七色に光ります。これは「干渉」や「回折」と呼ばれる、 波の特徴が光にも見られる証拠。
なので、「光は波です」という考えは、長い間正しいとされてきました。
干渉はまだしも……「回折」ってなんだろう?身近にあるかな?
でも……
2. 粒じゃなきゃ説明できない現象があった
ところが、ある実験で「光は波だけでは説明できないのでは?」という事態が起こります。
その実験とは、光を金属に当てると電子が飛び出すというもの。 これを「光電効果」といいます。
光を強くしても飛び出す電子のエネルギーが変わらず、 代わりに光の“色”によってエネルギーが変わる……?
この奇妙な現象を説明するには、 「光が粒(エネルギーの塊)として金属にぶつかっている」と考えるしかなかったのです。
つまり、「光はエネルギーをもった粒」としてふるまうことがある、と。
この粒のことを、光子(こうし/photon)と呼びます。
3. 結局どっちなの?
さて、ここで混乱しますね。
「じゃあ、波なの?粒なの?どっちなの?」
これに対する科学の答えは、
「どっちでもある」
です。はい、ちょっとズルいですよね。
でも本当にそうなんです。
光は、波のようなふるまい(干渉・回折)もするし、 粒のようなふるまい(衝突・エネルギー移動)もする。
これを「波動・粒子二重性」といいます。
波と粒って、そもそもどう違うんだろう?
4. 二重性を見せてくれる伝説の実験
この“二重性”を体感できる有名な実験があります。 それが「二重スリット実験」。
ざっくり言うと、光を2つのすきま(スリット)に通すと、 その先に“干渉模様”と呼ばれる縞模様が現れます。
これは波の性質。
でも、光子を一粒ずつ飛ばしても、 長く観察すると、やっぱり干渉模様ができるんです。
つまり、1粒の光子も「自分で波として干渉してる」ようなふるまいをする。
もうここまで来ると、 「光って“私たちの感覚”で説明できないものなんじゃ……」 という気がしてきますね。
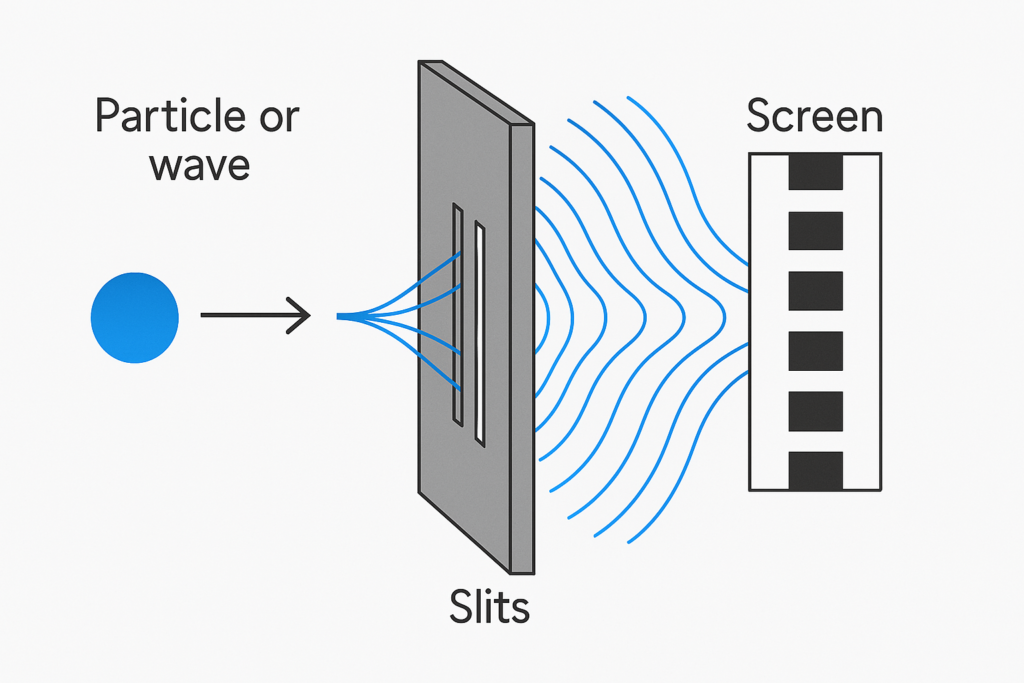
5. じゃあ、光の正体って?
光は「波」でもあり「粒」でもある。 でも、そのどちらでもない、もっと根本的な存在なのかもしれません。
科学はそれを「電磁波の一種」であると定義します。
電場と磁場が振動しながら空間を進むエネルギーの波。 それが光。
でも私たちはその「見え方」を通してしか光を知れない。 だからこそ、波として見たり、粒として感じたりするわけです。
電場と磁場って?何が振動してるの?
6. まとめ
- 光は昔「波」として理解されていた
- でも「粒(光子)」としてのふるまいも観測された
- 結果、「波と粒の二重性」を持つことがわかった
- つまり光は、見る方法によって姿を変える、不思議な存在
この問いは、次の問いにつながっていきます。
「波としての光は、どこまで届くのか?」 「粒としての光は、どこにたどり着くのか?」
そんな疑問に、次回は海の底からアプローチしてみようと思います。
光は、見るほどに、不思議。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!