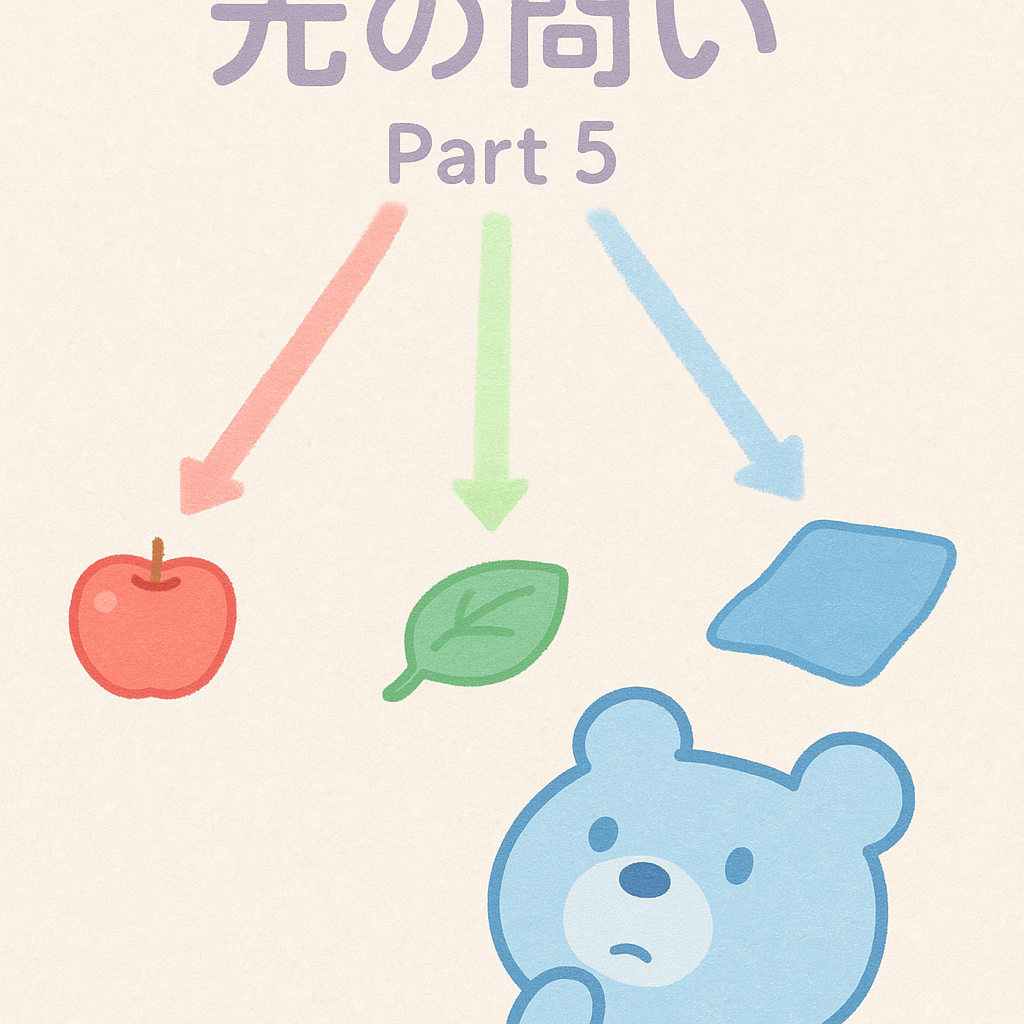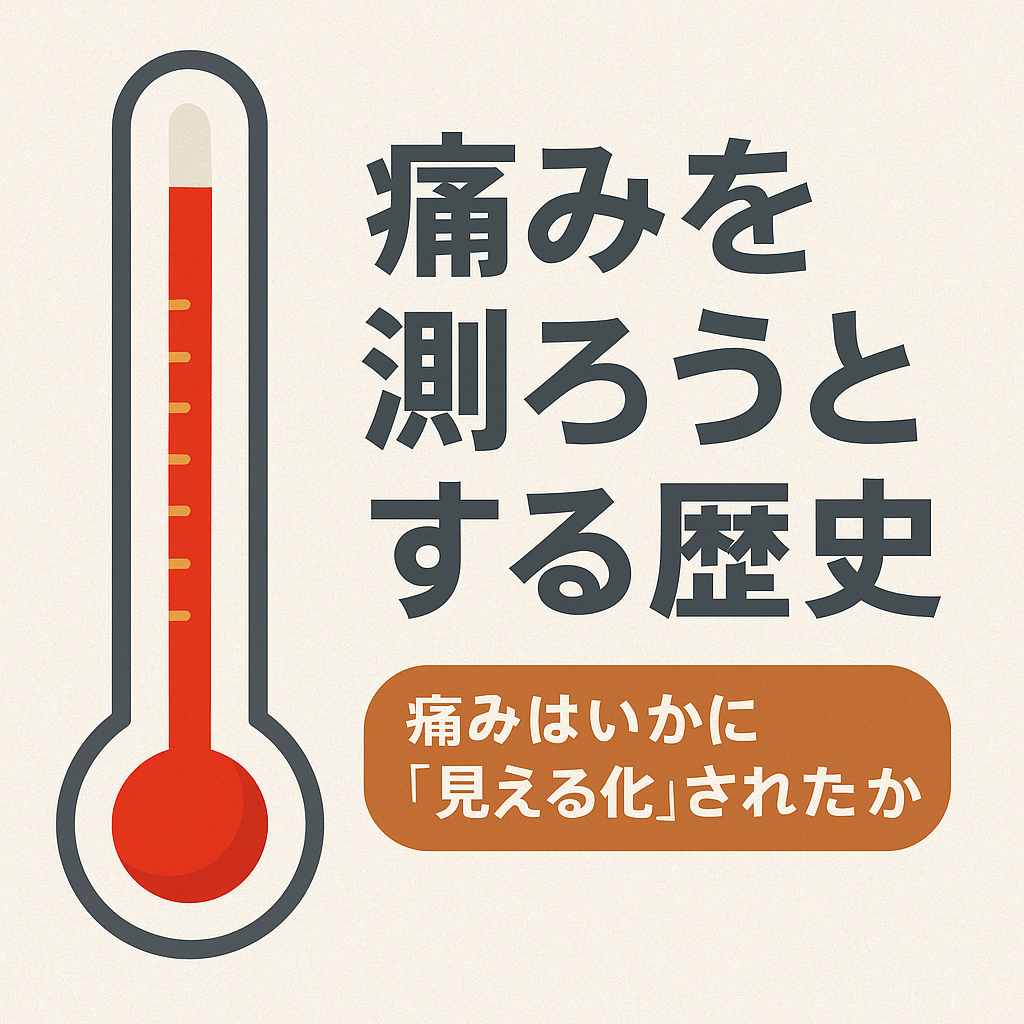「○○さーん?……はいー!」──テレビ中継の“タイムラグ”はなぜなくならない?

こんにちは。Sol@です。
テレビでよくあるあのやり取り、思い出しませんか?
アナウンサー「現地の○○さーん?」
画面の向こう「…………はいー!」
この微妙な“間”に、見ているこちらがちょっと笑ってしまう。
でも、ふと疑問が浮かびます。
「これって、まだ直らないの?」
「5Gとか言ってる時代に、なんでこんなタイムラグがあるの?」
今回はそんな“もはや定番”となった現象に光をあてて、
中継の裏側をやさしくコトトコしてみましょう!
1. タイムラグの正体は「距離」だけじゃない?
よく言われるのが「通信に時間がかかってるんでしょ?」という理由。
たしかにそれも一因です。でも、実際にはもっといろんな要素が重なってるんです。
2. 衛星通信の“距離”は想像以上に長い!
まず、テレビ中継でよく使われる「衛星通信」の仕組みを見てみましょう。
- 静止衛星は、地上から約36,000km上空
- 地上→衛星→中継地→スタジオというルートを取ると、片道約0.12秒、往復で約0.24秒
この時点で、すでに約0.2〜0.3秒の物理的遅延が発生しています。
さらに──
- 信号の変換や圧縮・解凍処理
- スタジオ側での音声・映像の同期調整
これらも加わって、合計で1秒前後の“間”が発生することがあるのです。
3. 映像と音声、それぞれ“別ルート・別処理”
ここも大事なポイント。
- 映像はデータ量が大きく、圧縮処理に時間がかかる
- 音声は軽いが、人間はズレに敏感なので“きっちり揃える”必要がある
- つまり:別々の処理をした上で、“一緒に見せる”ために調整が必要
実際の中継では、音声が映像に先行しすぎないように“あえて遅らせる”こともあります。
→ この「調整のための間」が、あの「……はいー!」の正体なんですね。
4. 5Gでは解決できないの?
「今は5Gとか光回線とか、高速通信じゃないの?」
確かに私たちの日常では高速通信が広がっています。
でも──
- 5Gはスマホや近距離デバイス向けの通信技術
- テレビ中継は専用の回線・衛星・中継車を使うケースが多い
- → 通信網がそもそも別
また、スタジオ→中継地→報道局と、いくつものシステムを通過するため、
「処理や調整の時間」がどうしても積み重なってしまうのです。
5. それでも、ラグが残る理由は?
- 技術的には、縮める工夫はされている(光ファイバーやIP中継など)
- でもそれでも0.5〜1秒のラグは“許容範囲”として残されているのが現状
なぜか?
✅「完全なリアルタイム」は、コストと信頼性のバランスが取れない
- 高速化すればするほど、機器も通信も高額に
- タイムラグ1秒で済むなら、視聴者の体験として“問題にならない”
つまり、少しの間なら許される“テレビ的お約束”になっているわけなんです。
6. まとめ:あの“間”にも、意味があった
- テレビ中継で起こるタイムラグは、通信距離・処理工程・同期調整の複合的な結果
- 特に衛星通信は距離が長く、遅延が物理的に避けられない
- 音声と映像の“ズレ”をなくすには、あえて調整で“間”を作る必要がある
- 5Gなどの通信技術は、テレビの業務中継とは別の世界で使われている
- ラグは「時代遅れ」ではなく、「合理的な選択」の結果かもしれない
次に「○○さーん?……はいー!」を見たとき、
それがただの“もたつき”じゃなく、
いくつもの技術と人の調整が重なった結果だと思い出してみてください。
そして何より、あのちょっと間の抜けた“間”にも、
どこか人間らしいあたたかさがあるのかもしれませんね。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました!
それではまた、次のコトトコでお会いしましょう🛰️📡