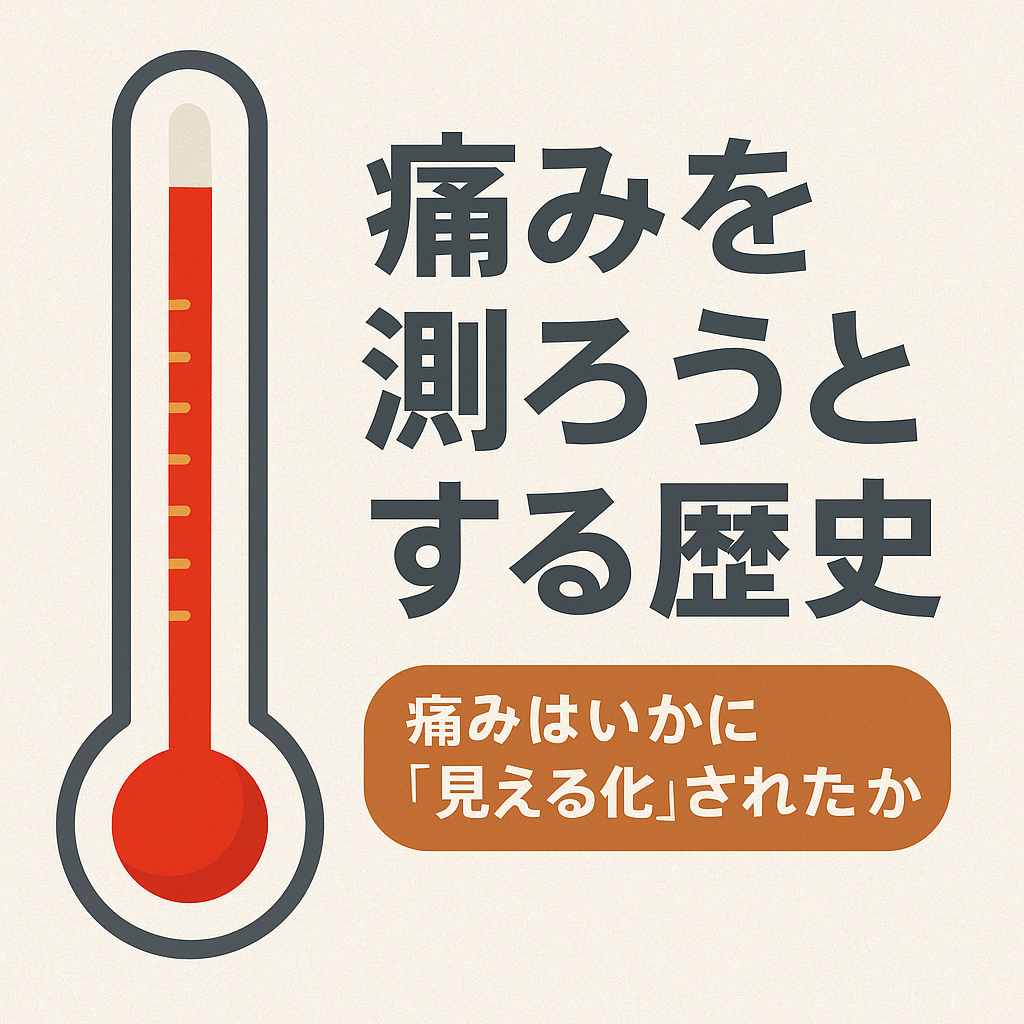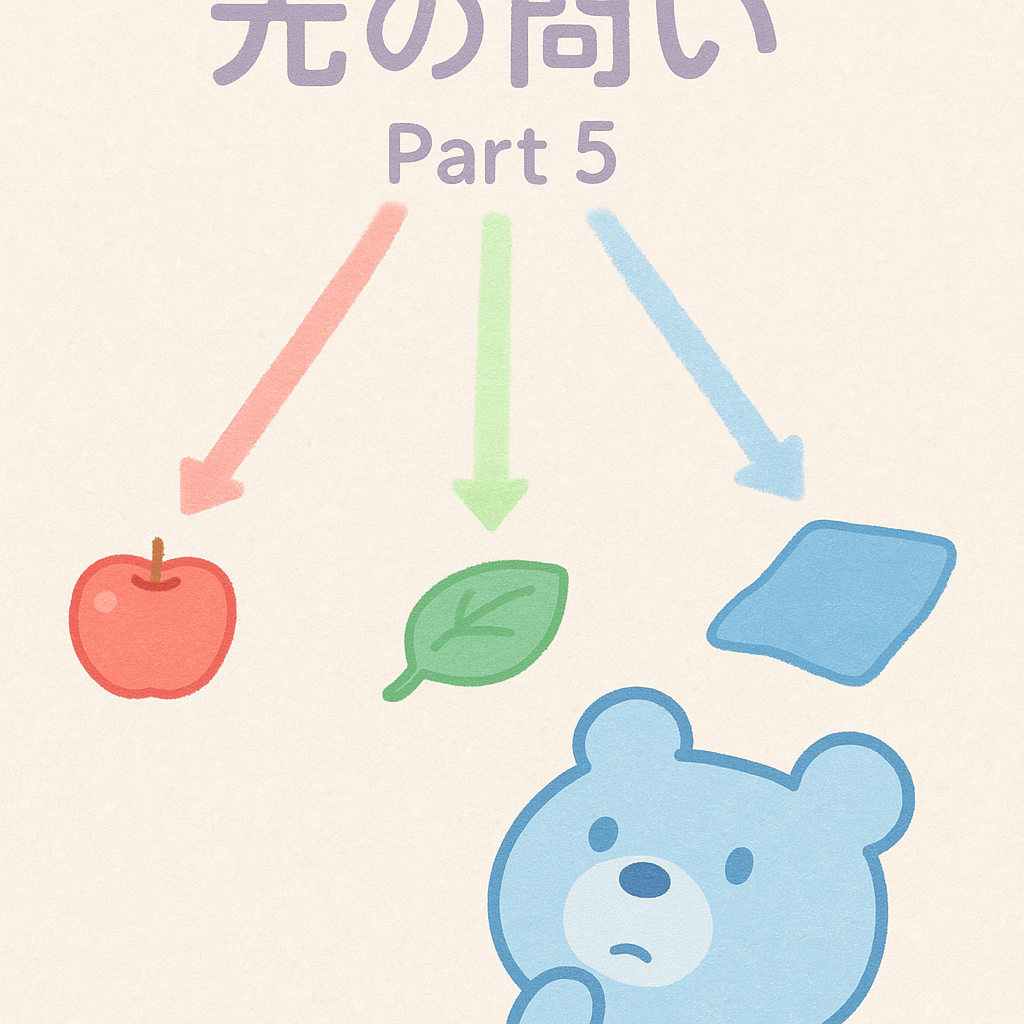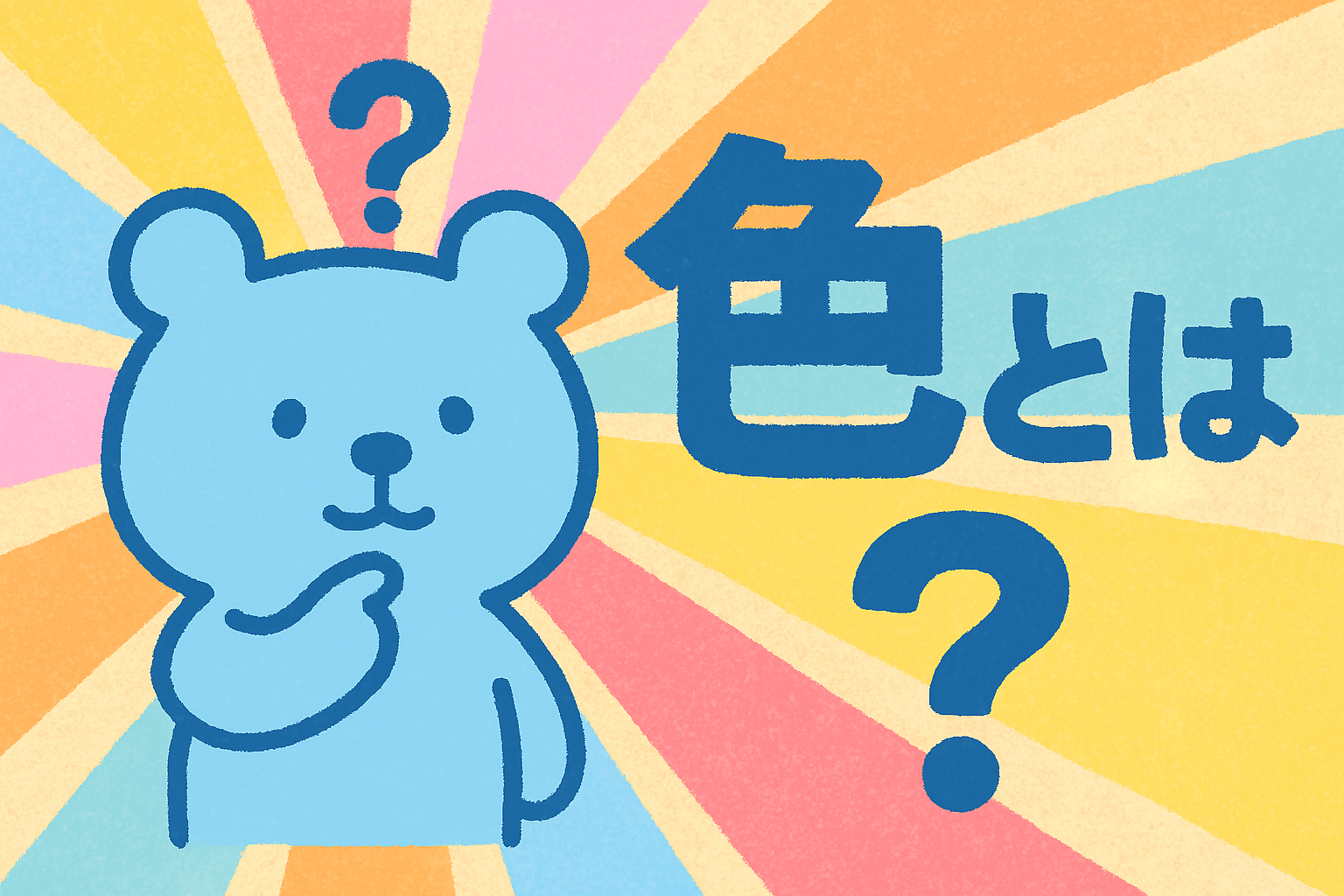海の底で光はどうなる?なくなっちゃうの…?

こんにちは。Sol@です。
前回の問い、「光って粒?波?」では、 “光というものの正体”について少し覗いてみました。 粒のようにふるまうし、波のようにもふるまう。 そしてそのどちらでもある、ふしぎな存在。
前回リンク:光って、粒なの?波なの?……なんなの!?
では、その“ふしぎな存在”である光が、 たとえば「海の底」に届くとき、どうなるのでしょうか?
今回は、そんな「光の行き先」にまつわる問いを、 一緒にゆるっと、でもじっくり考えてみたいと思います!
1. 光は、深くなると届かなくなる?
水族館の深海コーナーなどで、 「太陽の光は深海には届かない」といった説明を見たことがある方も多いかもしれません。
でも、光は真っすぐ飛んでくるもののはず。 ならば、「どこかでストップする」のではなく、 「薄くなっていく」「消えていく」感覚に近いんです。
そこではどんなことが起こっているのでしょうか?消えていく光はどこへ行ってしまったのでしょうか??
2. 光は“吸収”されたり、“散乱”したりしている
海に入った光は、まず水面で一部が反射されます。 そして、水の中に入った光は「吸収」や「散乱」によって少しずつ弱まっていきます。
- 吸収:光のエネルギーが水の分子に取り込まれ、熱などに変わる
- 散乱:水の中の小さな粒子にぶつかって、光がいろんな方向にバラける
これが何度も何度も起こるうちに、 やがて光は目に見えないほど弱くなり、届かなくなってしまうのです。
「エネルギーが吸収される」って、どこへ行くの?
3. 実は、波長によって“残りやすさ”が違う
ここで面白いのが、光の「色」によって届く深さが違うこと。
赤い光は浅いところですぐに吸収されてしまい、 青い光は深いところまで届く——
これは、光の波長の違いによって、水分子との相性が違うから。
長い波長(赤外線や赤)は水に吸収されやすく、 短い波長(青や紫)は比較的通りやすいんですね。
なので、海の中はどんどん“青く”見えるようになります。
青く見えるのは、青い光が残ってるから?それとも反射してるから?
吸収される波長ってどうやって決まるんだろう…?
4. じゃあ、海の底に光子は届いてないの?
さて、「粒」としての光——つまり光子はどうでしょうか?
実は、水中に届く光子の多くも、 途中で吸収されたり、進路が乱れたりしてしまいます。
たとえば、赤い光子はすぐに水分子に吸収されて“熱”として散ってしまいますし、 青い光子も、どこかの時点で必ず消失します。
つまり、光子が「たまっている」わけではなく、 すべてどこかで“使われて”いるんですね。
5. まるでやさしい伝言ゲームのように
ここまでの話をたとえるなら、 光は「やさしい伝言ゲームのようなもの」かもしれません。
誰かが太陽から受け取ったエネルギーを、 少しずつ周囲に渡しながら、最後には海の奥底に届く前に消えていく。
消えるというより、「役目を終える」——そんな感じです。
だからこそ、海の底は暗い。 でもその暗さは、「光が届かなかった」のではなく、 「光がすべて、どこかで使われた」結果なんですね。
6. まとめ
- 光は海の中で吸収・散乱されてどんどん減っていく
- 色(波長)によって届く深さが違う(青は残りやすい)
- 光子も、最終的にはエネルギーとして使われていく
- 海の底が暗いのは、「光が届かない」のではなく「使い切られている」から
次回の問いは、そこからもう少し視点を広げて—— 「そもそも“色”ってなんだろう?」 「私たちは何を“見ている”のか?」
という不思議へ、トコトコ歩いていこうと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!